2008年02月04日
青木勝幸さん
バンデロール(沼津市)第2営業部長
青木勝幸(あおきかつゆき)さん
首都圏の販路拡大目指す
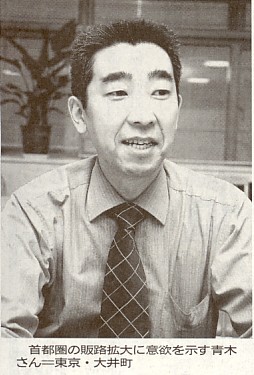 大手パンメーカーから沼津市に本部を置く沼津ベーカリー関連の「バンデロール」に移って十年。首都圏への販路拡大を目指して昨年十二月、横浜市内にあったオフィスを東京・大井町に移した。川崎市出身、四十四歳。
大手パンメーカーから沼津市に本部を置く沼津ベーカリー関連の「バンデロール」に移って十年。首都圏への販路拡大を目指して昨年十二月、横浜市内にあったオフィスを東京・大井町に移した。川崎市出身、四十四歳。
ー都内にオフィスを移した狙いを教えてください。
「現在、首都圏の店舗は二十二。店長会議を開く際に集まりやすいアクセスの良さがありました。情報を発信するにはやはり東京。近隣には競合店もあり、情報収集をしやすいという利点もあります」
ー首都圏の魅力は何でしょう。
「首都圏での売り上げは会社全体の四割。三月から五月にかけて新たに店舗をオープンさせる予定です。一店舗当たりの売り上げが高く、利益額も大きいのが魅力。一方でお客さんの要求が高いのも事実で、周囲との競合に知恵を出さなければ生き残っていけません」
ー首都圏での販売戦略を教えてください。
「焼きたてのパンを試食いただき、買っていただく。商品の見せ方、販売には自信があります。さらに品質を高めていく努力を続けていきたいと思います。将来的には、レストランを兼ねた路面店舗を展開したいと考えています」
ー業界の課題はありますか。
「従業員数は減少傾向にあります。少人数でも店舗運営できるように仕組みを変えていく必要があります。原油高で小麦やチーズの値段が高騰しています。昨年十二月に一部商品の値上げをしましたが、四月にもう一度見直さざるを得ない現状です」
(静新平成20年2月4日「インタビュー」)
青木勝幸(あおきかつゆき)さん
首都圏の販路拡大目指す
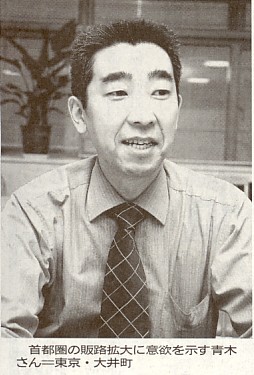 大手パンメーカーから沼津市に本部を置く沼津ベーカリー関連の「バンデロール」に移って十年。首都圏への販路拡大を目指して昨年十二月、横浜市内にあったオフィスを東京・大井町に移した。川崎市出身、四十四歳。
大手パンメーカーから沼津市に本部を置く沼津ベーカリー関連の「バンデロール」に移って十年。首都圏への販路拡大を目指して昨年十二月、横浜市内にあったオフィスを東京・大井町に移した。川崎市出身、四十四歳。ー都内にオフィスを移した狙いを教えてください。
「現在、首都圏の店舗は二十二。店長会議を開く際に集まりやすいアクセスの良さがありました。情報を発信するにはやはり東京。近隣には競合店もあり、情報収集をしやすいという利点もあります」
ー首都圏の魅力は何でしょう。
「首都圏での売り上げは会社全体の四割。三月から五月にかけて新たに店舗をオープンさせる予定です。一店舗当たりの売り上げが高く、利益額も大きいのが魅力。一方でお客さんの要求が高いのも事実で、周囲との競合に知恵を出さなければ生き残っていけません」
ー首都圏での販売戦略を教えてください。
「焼きたてのパンを試食いただき、買っていただく。商品の見せ方、販売には自信があります。さらに品質を高めていく努力を続けていきたいと思います。将来的には、レストランを兼ねた路面店舗を展開したいと考えています」
ー業界の課題はありますか。
「従業員数は減少傾向にあります。少人数でも店舗運営できるように仕組みを変えていく必要があります。原油高で小麦やチーズの値段が高騰しています。昨年十二月に一部商品の値上げをしましたが、四月にもう一度見直さざるを得ない現状です」
(静新平成20年2月4日「インタビュー」)
2008年02月04日
一条兼良
「一条兼良」
源氏物語千年:島内景二
一条兼良、近代的研究の源
一四六七年に応仁の乱が起き、下克上の戦国時代が始まった。信じられるのは、自分の目で見、自分の耳で聞いたものだけ。混乱とひきかえに、合理的精神が日本全国に広く行き渡った。
 合理主義者が、古典を読んだらどうなるか。例えば伊勢物語に「女」とあれば、ただの「女」と解釈すべきで、二条の后がモデルだとか小野小町のことだとか空想するのはもってのほか、ということになる。
合理主義者が、古典を読んだらどうなるか。例えば伊勢物語に「女」とあれば、ただの「女」と解釈すべきで、二条の后がモデルだとか小野小町のことだとか空想するのはもってのほか、ということになる。
それが、一条兼良(一四〇二ー一四八一年)の信条だった。合理主義者の彼は、足利義政の妻で、実質的な幕府の最高権力者、日野富子に取り入った。「日本はアマテラス以来、女性が支配者だとうまく治まる」などと、著書で述べている。
兼良は、関白太政大臣まで上りつめた。しかも、「学問の神様」である菅原道真よりも自分の知識量が優れていると自負していた。彼が著した「花鳥余情」(かちようよせい)には、「我が国の至宝は、源氏の物語に過ぎたるはなかるべし」とある。
おそらく、自分以前の源氏研究は不十分で、自分が史上初めて、源氏物語が宝であるゆえんを解明したと信じたのだろう。ここに、近代的な源氏研究の源がある。
兼良が得意としたのは、「文脈」と「分類」の二つ。彼以前の研究は、「語釈=単語」にとどまっていた。言葉は、単語が連なった文章となって初めて意味を持つ。同じ言葉でも、文脈次第で意味が変わってくる。
四辻善成の研究で、一つの単語はすべての個所で同じ意味だとされていたのとは段違いである。
兼良の優れた分析力は、五十四の巻名を四つに分類した点に表れている。「その巻の歌の言葉から取った」「その巻の散文の言葉」「和歌にも散文にもある」「和歌にも散文にもない」の四分類である。これは、現代の市販されているほとんどすべてのテキストに踏襲されている。
一族が血で血を洗い、平和が失われた時代に、現在の高等学校の古文教育上の「基本理念」が確立していたのである。兼良は、源氏物語を近代人の解釈にたえる古典にまで高めた恩人である。だが、夢や空想力が失われた側面もある。ここが、源氏物語の分岐点だったかもしれない。(電気通信大教授)
(静新平成20年2月4日「命をつないだひとたち」)
源氏物語千年:島内景二
一条兼良、近代的研究の源
一四六七年に応仁の乱が起き、下克上の戦国時代が始まった。信じられるのは、自分の目で見、自分の耳で聞いたものだけ。混乱とひきかえに、合理的精神が日本全国に広く行き渡った。
 合理主義者が、古典を読んだらどうなるか。例えば伊勢物語に「女」とあれば、ただの「女」と解釈すべきで、二条の后がモデルだとか小野小町のことだとか空想するのはもってのほか、ということになる。
合理主義者が、古典を読んだらどうなるか。例えば伊勢物語に「女」とあれば、ただの「女」と解釈すべきで、二条の后がモデルだとか小野小町のことだとか空想するのはもってのほか、ということになる。それが、一条兼良(一四〇二ー一四八一年)の信条だった。合理主義者の彼は、足利義政の妻で、実質的な幕府の最高権力者、日野富子に取り入った。「日本はアマテラス以来、女性が支配者だとうまく治まる」などと、著書で述べている。
兼良は、関白太政大臣まで上りつめた。しかも、「学問の神様」である菅原道真よりも自分の知識量が優れていると自負していた。彼が著した「花鳥余情」(かちようよせい)には、「我が国の至宝は、源氏の物語に過ぎたるはなかるべし」とある。
おそらく、自分以前の源氏研究は不十分で、自分が史上初めて、源氏物語が宝であるゆえんを解明したと信じたのだろう。ここに、近代的な源氏研究の源がある。
兼良が得意としたのは、「文脈」と「分類」の二つ。彼以前の研究は、「語釈=単語」にとどまっていた。言葉は、単語が連なった文章となって初めて意味を持つ。同じ言葉でも、文脈次第で意味が変わってくる。
四辻善成の研究で、一つの単語はすべての個所で同じ意味だとされていたのとは段違いである。
兼良の優れた分析力は、五十四の巻名を四つに分類した点に表れている。「その巻の歌の言葉から取った」「その巻の散文の言葉」「和歌にも散文にもある」「和歌にも散文にもない」の四分類である。これは、現代の市販されているほとんどすべてのテキストに踏襲されている。
一族が血で血を洗い、平和が失われた時代に、現在の高等学校の古文教育上の「基本理念」が確立していたのである。兼良は、源氏物語を近代人の解釈にたえる古典にまで高めた恩人である。だが、夢や空想力が失われた側面もある。ここが、源氏物語の分岐点だったかもしれない。(電気通信大教授)
(静新平成20年2月4日「命をつないだひとたち」)



