2015年12月27日
浜悠人さんが『乾坤めぐりて』
沼津朝日新聞投稿文を編み
浜悠人さんが『乾坤めぐりて』
今年の刊行本から

沼津朝日新聞の投稿欄で「浜悠人」のペンネームで知られる佐野利夫さんが今秋、これまでの投稿から選んだ一一八編を収録したエッセイ集『乾坤めぐりて』=写真=を上梓した。
乾坤は「天と地」の意。この書名について浜さんは「あとがき」で「自分の人生の変遷に思いをいたすことからつけた」といい、「母校、沼津東高の応援歌、乾坤めぐりての一節『乾坤めぐりて幾春を迎え送りて今日此処に…』が脳裏に浮かぶ」と書いている。表紙の書名は浜さんの妻、佐野忠子さんの揮毫による。
収録されたのは、平成七年三月八日から今年一月二十五日までの間に掲載された中からの作品。浜さんは高校で教鞭を執り、退職後、東高の校史編纂に携わったが、その中で、旧制中学時代に遡る先輩達の業績や活動を知り、随筆として書き始めた。
また、趣味の会で学んだ沼津の歴史や文学、市内の散策や旅先で触れた史実とか出来事とかについて、改めて資料に当たり、それぞれ一文にした。
とりわけ母校の先輩や郷土の先達、沼津兵学校ゆかりの人物などを積極的に取り上げ、各地、各方面で活躍した様子を紹介している。
特筆すべきは「町名由来」シリーズ。当初「町名由来板」として、市街地の旧町名紹介に始まったのが周辺に拡大。「正」から「続」となり「続続」まで十九編に及んだ。特に人気を呼んだ投稿で、沼津朝日新聞社にはバックナンバーを求める依頼も相次ぐ一方、浜さんが小規模学習会で講師を務めるまでになった。
この十九編のほか、同書に収められた作品を分類すると、人物にちなんだ六十編、石碑について十編、廃線を訪ねた四編、旅行などによる二十五編。各編の中には、文章ゆかりの写真や地図が掲載されたものもあり、文章への関心をより高める効果で成功している。
また、新聞に掲載されたものなので、いずれも知っているはずなのに、読み直すと、改めて思いを新たにするものが多く、今後、沼津再発見、沼津発信の材料になりそうだと感じたところもある。
一一八編のトップバッターを務めたのは「風雲児・山崎劔二」。市議、県議、衆院議員として活躍する一方、ボルネオに渡ると現地の行政にも関わり、帰国して再び沼津市議となったが、昭和二十九年、ブラジルに渡って彼の地で客死した一大の風雲児を扱った。
以下、沼津ゆかりの多くの人物を取り上げ、活躍の様子が描かれるが、戦争にまつわる点描も数多く、特攻兵や回天、戦死した義兄、原爆のことなどに触れ、また戦時中の思想統制にも言及しながら、平和への思いを刻んでいる。
同書は二七〇ページ。天野出版工房刊。非売品で、友人、知人、同窓会関係者らに贈呈したが、八十部程残部があり、希望者には進呈するという。
問い合わせは佐野利夫さん(電話九六三ー三九四五)。
【沼朝平成27年12月27日(日)号】
浜悠人さんが『乾坤めぐりて』
今年の刊行本から

沼津朝日新聞の投稿欄で「浜悠人」のペンネームで知られる佐野利夫さんが今秋、これまでの投稿から選んだ一一八編を収録したエッセイ集『乾坤めぐりて』=写真=を上梓した。
乾坤は「天と地」の意。この書名について浜さんは「あとがき」で「自分の人生の変遷に思いをいたすことからつけた」といい、「母校、沼津東高の応援歌、乾坤めぐりての一節『乾坤めぐりて幾春を迎え送りて今日此処に…』が脳裏に浮かぶ」と書いている。表紙の書名は浜さんの妻、佐野忠子さんの揮毫による。
収録されたのは、平成七年三月八日から今年一月二十五日までの間に掲載された中からの作品。浜さんは高校で教鞭を執り、退職後、東高の校史編纂に携わったが、その中で、旧制中学時代に遡る先輩達の業績や活動を知り、随筆として書き始めた。
また、趣味の会で学んだ沼津の歴史や文学、市内の散策や旅先で触れた史実とか出来事とかについて、改めて資料に当たり、それぞれ一文にした。
とりわけ母校の先輩や郷土の先達、沼津兵学校ゆかりの人物などを積極的に取り上げ、各地、各方面で活躍した様子を紹介している。
特筆すべきは「町名由来」シリーズ。当初「町名由来板」として、市街地の旧町名紹介に始まったのが周辺に拡大。「正」から「続」となり「続続」まで十九編に及んだ。特に人気を呼んだ投稿で、沼津朝日新聞社にはバックナンバーを求める依頼も相次ぐ一方、浜さんが小規模学習会で講師を務めるまでになった。
この十九編のほか、同書に収められた作品を分類すると、人物にちなんだ六十編、石碑について十編、廃線を訪ねた四編、旅行などによる二十五編。各編の中には、文章ゆかりの写真や地図が掲載されたものもあり、文章への関心をより高める効果で成功している。
また、新聞に掲載されたものなので、いずれも知っているはずなのに、読み直すと、改めて思いを新たにするものが多く、今後、沼津再発見、沼津発信の材料になりそうだと感じたところもある。
一一八編のトップバッターを務めたのは「風雲児・山崎劔二」。市議、県議、衆院議員として活躍する一方、ボルネオに渡ると現地の行政にも関わり、帰国して再び沼津市議となったが、昭和二十九年、ブラジルに渡って彼の地で客死した一大の風雲児を扱った。
以下、沼津ゆかりの多くの人物を取り上げ、活躍の様子が描かれるが、戦争にまつわる点描も数多く、特攻兵や回天、戦死した義兄、原爆のことなどに触れ、また戦時中の思想統制にも言及しながら、平和への思いを刻んでいる。
同書は二七〇ページ。天野出版工房刊。非売品で、友人、知人、同窓会関係者らに贈呈したが、八十部程残部があり、希望者には進呈するという。
問い合わせは佐野利夫さん(電話九六三ー三九四五)。
【沼朝平成27年12月27日(日)号】
2015年12月26日
田村俊子さん
田村俊子さんが歌文集「花吹雪」
自身の半生と花柳流の歴史振り返る
今年の刊行本から

花柳流日本舞踊、香道・茶道安藤家御家流、石水流盆石の各師範、田村俊子さん(89)は、卆寿を前に、歌文集「花吹雪」を発刊した。昭和十五年ごろから書きためてきた短歌を掲載し、夫の故花柳稔(田村稔)氏と歩んだ花柳流の歴史を写真で紹介。戦中や戦後復興期の沼津を詠った短歌、随筆を掲載した百九十八ページ。
田村さんは大正十五年、真砂町生まれ。昭和十五年、十五歳の時に駿河(現スルガ)銀行に就職し、二十一年に職場での勧めもあり日本舞踊花柳流花柳稔師に入門し、二十三年に花柳師と結婚。
花柳咲海として舞踊の舞台に立つとともに、後進を指導する一方、茶道、香道、盆石の師範となり、水墨画、ちぎり絵、大和絵も趣味で描く。
短歌は五十六年、東海短歌に入会して本格的に取り組むようになり、久田次郎氏(故人)に師事。久田氏が「寸信」創刊と同時に同人となり、二十三年に終刊するまで投稿。久田氏からは生前、歌集の出版を強く勧められていたが実現せず、その間、平成十七年には稔師を亡くした。
二十四年には、五十年来の付き合いがある居山郁子さんが主宰する茜塾に入り、短歌結社「沃野」に入会して三枝浩樹氏に師事。居山さんの協力で歌文集の発刊が実現した。
歌文集には駿河銀行入社時の記念写真から舞台での姿まで写真や文章を掲載している。
花柳流に関する歌も多く、亡き夫を詠ったものもあるが、戦時中に防空壕に隠したため焼失を免れたという短歌の中から抜粋し、戦死した兄を思う歌のほか、「かぼちゃ畑にうずくまり居りし空襲の夜 今は新たに生きねばならぬ」など当時の心境を詠ったものも。
晩年は孫、ひ孫と過ごす穏やかな日々を詠い「公園で旭と遊べば陽に光る花は珍し黄金桜よ」、孫の活躍を詠った「二二三の日御用邸には人あふれ孫の『序の舞』光まばゆき一など。
沼津朝日の沼津歌壇に投稿した歌の中から、「沃野」の東京大会で評価が高かった「米寿越して身の丈ちぢむ齢となりぬ木綿針もて作務衣なおす」などがあり、随筆は十編を掲載している。
田村さんは「写真と短歌を通して花柳流と、主人も愛した沼津の復興の歴史を語りたかった」と話している。
歌文集は二千五百円。二十七日までマルサン書店仲見世店に並ぶほか、吉田町の文化サロンからすうりでも扱っている。
【沼朝平成27年12月26日(土)号】
自身の半生と花柳流の歴史振り返る
今年の刊行本から

花柳流日本舞踊、香道・茶道安藤家御家流、石水流盆石の各師範、田村俊子さん(89)は、卆寿を前に、歌文集「花吹雪」を発刊した。昭和十五年ごろから書きためてきた短歌を掲載し、夫の故花柳稔(田村稔)氏と歩んだ花柳流の歴史を写真で紹介。戦中や戦後復興期の沼津を詠った短歌、随筆を掲載した百九十八ページ。
田村さんは大正十五年、真砂町生まれ。昭和十五年、十五歳の時に駿河(現スルガ)銀行に就職し、二十一年に職場での勧めもあり日本舞踊花柳流花柳稔師に入門し、二十三年に花柳師と結婚。
花柳咲海として舞踊の舞台に立つとともに、後進を指導する一方、茶道、香道、盆石の師範となり、水墨画、ちぎり絵、大和絵も趣味で描く。
短歌は五十六年、東海短歌に入会して本格的に取り組むようになり、久田次郎氏(故人)に師事。久田氏が「寸信」創刊と同時に同人となり、二十三年に終刊するまで投稿。久田氏からは生前、歌集の出版を強く勧められていたが実現せず、その間、平成十七年には稔師を亡くした。
二十四年には、五十年来の付き合いがある居山郁子さんが主宰する茜塾に入り、短歌結社「沃野」に入会して三枝浩樹氏に師事。居山さんの協力で歌文集の発刊が実現した。
歌文集には駿河銀行入社時の記念写真から舞台での姿まで写真や文章を掲載している。
花柳流に関する歌も多く、亡き夫を詠ったものもあるが、戦時中に防空壕に隠したため焼失を免れたという短歌の中から抜粋し、戦死した兄を思う歌のほか、「かぼちゃ畑にうずくまり居りし空襲の夜 今は新たに生きねばならぬ」など当時の心境を詠ったものも。
晩年は孫、ひ孫と過ごす穏やかな日々を詠い「公園で旭と遊べば陽に光る花は珍し黄金桜よ」、孫の活躍を詠った「二二三の日御用邸には人あふれ孫の『序の舞』光まばゆき一など。
沼津朝日の沼津歌壇に投稿した歌の中から、「沃野」の東京大会で評価が高かった「米寿越して身の丈ちぢむ齢となりぬ木綿針もて作務衣なおす」などがあり、随筆は十編を掲載している。
田村さんは「写真と短歌を通して花柳流と、主人も愛した沼津の復興の歴史を語りたかった」と話している。
歌文集は二千五百円。二十七日までマルサン書店仲見世店に並ぶほか、吉田町の文化サロンからすうりでも扱っている。
【沼朝平成27年12月26日(土)号】
2015年12月26日
矢田凡久(保久)さん
元政治家秘書 矢田凡久(保久)さん
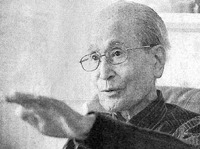
「 やた・ぼんきゅう==やすひさ 1915年11月30日、小山町生まれ。8人きょうだいの長男として、町立成美小一沼津中(現沼津東高)に進んだ。卒業後は紀伊国屋書店や日本読書新聞社などで働き、近衛歩兵第2連隊、支那駐屯歩兵第2連隊に転属した。53年から遠藤三郎氏の秘書に就き、遠藤氏が他界した後は富士通や東タイなどで勤務。原田昇左右氏の統括責任者として選挙を担い、9回連続当選を支えた。沼津市企画部長のほか、市内の企業や医療法人の役員などさまざまな職を経て、85歳で職業的な仕事から引退した。」
政治の大切さを痛感
東名高速道や首都高速道の建設、狩野川台風の被災地復旧などに尽力した裾野市出身の政治家故遠藤三郎。旧衆院静岡2区で連続9期当選し、岸信介内閣で建設相を務めた大物を県東部の選挙区で秘書として支えた一人が、小山町出身の矢田凡久(本名・保久)さん(99)=沼津市=。政治家秘密の世界に飛び込み、遠藤の地元筆頭秘書として若かりし日の自民党総務会長の二階俊博氏らを育ててきた。数奇な縁からさまざまな職を経験した。今年11月に100歳。今でもその人望は厚い。
◇
政治家秘書は主人本位の一体感で臨まなければできません。経験を通じて政治ほど大変なことはなく、政治ほど大切なことはないと痛感しました。秘書に就いたきっかけは沼津中(現県立沼津東高)の恩師で、私たち夫婦の媒酌人だった前田千寸先生が「沼中卒の秘書になれる人を探している」と声を掛けてくれたこと。1953年1月から遠藤先生の沼津市の事務所で、書生ら5人ほどの取りまとめ役として働くことになりました。秘書としての始まりでした。
携わった選挙は3回目から。先輩秘書に教わりながら富士川以東の支援者回りなどを続け、血の小便が出たこともあったほど。遠藤先生が建設相として入閣して大臣秘書官を務めるなど選挙や秘書の仕事から多くの人脈ができました。二階俊博先生もその一人。中央大卒業後に秘書に加わり、選挙区にも頻繁に訪れてくれました。
秘書同士が立場を超えてまとまる場として「初心会」を発足しました。保守合同前の民主党幹事長だった岸信介氏が筆頭副幹事長の遠藤先生に贈った「初心忘るべからず」の一幅に由来しています。遠藤先生の命日12月27日を中心に集まって、しのんできました。
りーダーの資質学ぶ
遠藤先生は寡黙で地元のために献身した人でした。高速道路をめぐり東名か中央かどちらを先に着工するかという問題では意見を言いませんでした。土地を取られる農家に配慮した行動です。やると決断した時、決断後の行動は迅速でした。リーダーとして機を見るタイミング、決断すれば一気に動く行動力などを肌で学びました。
好きな書葉に「即離即覚(そくりそっかく)」があります。選挙に負けてもとちわれずに次を考える。くよくよしても仕方がないという意味です。遠藤先生の長兄が裾野市長選で敗れた時の言葉で、選挙の戦訓が万事に当てはまると自戒しています。遠藤先生は首都高速建設も力を注ぎ、首都高速道路公団が設立されると、私は秘書から公団調査役になり、遠藤先生の支援者でつくる遠藤会の原精一氏が沼津市長に当選した年からは、先生に言われて市企画部長として勤務しました。御用邸の払い下げ、東海大誘致などの課題を抱えていました。どれもこれまでに得た人脈が生き、実現や解決につながったと思います。
絶え間ない縁
書店の小僧から始まった人生を振り返ると、何回職業を変えたことか。行きたいという自分の意思で行ったところは一つもありません。次から次へと絶え間ない縁を与えてもらい、縁に従って生きた、いわば「随縁」です。縁は不思議です。どこでもここで一生働く気持ちで懸命に取り組んだ結果が次の縁につながってきたのではと思ったりもしますが、分かりません。
戦後70年です。真実を伝えることが生き残った人間の役目ですが難しい。近衛歩兵第2連隊に入隊し、翌年二・二六事件に巻き込まれました。戒厳令下鎮圧部隊の日々は忘れられない。その後は中国で第27師団支那駐屯歩兵第2連隊に転属し、師団司令部参謀部の作戦教育所属として打通作戦(大陸縦断作戦)にも参加しました。敗戦は広東から転進する途中で聞き、復員したのは31歳でした。
平和追求の努力を
仲間とともに戦後の郷土のために未来の道筋を考える場として「沼津自由大学講座」を企画しました。芹沢光治良や林芙美子、美濃部亮吉など各界を代表する人を講師に迎え、文化運動として結実しました。
「戦争はないほうが良い」。
誰もがそう思うでしょう。戦争をなくすためには、平素から皆で話し合い、英知を尽くして順序を踏んで平和を追求する努力をしなければならない。立派な政治家を輩出し、世界各国と話し、国内的には大同団結しないといけないでしょう。非常の時には非常の人が出てこないと非常を突破できません。
富士山に登るにもいくつもの道があります。一つの道でつっかえたら別の道を進む。道は一つではありません。お互いに助け合って良い方向を目指してほしい。同じ時代を生きているのだから。
『 遠藤三郎(1904-1971年)裾野市(旧富岡村)出身。旧制沼津中、第一高等学校、東京帝国大法律学科卒。農林省に進み食糧庁企画課長、和歌山県経済部長、農林省畜産局長などを歴任。1949年の総選挙で旧静岡2区より立候補して初当選し、衆院議員を連続9期務めた。大蔵政務次官や建設相のほか、自民党では副幹事長や政調副会長などの重職に就き、国土開発や農林水産業振興などに力を注いだ。狩野川台風の復旧には建設相として陣頭に立って対応した。』
(東部総局・杉山武博・宮崎隆男)
【静新平成27年5月1日「生きる」】
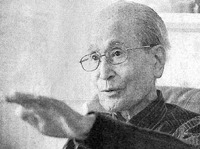
「 やた・ぼんきゅう==やすひさ 1915年11月30日、小山町生まれ。8人きょうだいの長男として、町立成美小一沼津中(現沼津東高)に進んだ。卒業後は紀伊国屋書店や日本読書新聞社などで働き、近衛歩兵第2連隊、支那駐屯歩兵第2連隊に転属した。53年から遠藤三郎氏の秘書に就き、遠藤氏が他界した後は富士通や東タイなどで勤務。原田昇左右氏の統括責任者として選挙を担い、9回連続当選を支えた。沼津市企画部長のほか、市内の企業や医療法人の役員などさまざまな職を経て、85歳で職業的な仕事から引退した。」
政治の大切さを痛感
東名高速道や首都高速道の建設、狩野川台風の被災地復旧などに尽力した裾野市出身の政治家故遠藤三郎。旧衆院静岡2区で連続9期当選し、岸信介内閣で建設相を務めた大物を県東部の選挙区で秘書として支えた一人が、小山町出身の矢田凡久(本名・保久)さん(99)=沼津市=。政治家秘密の世界に飛び込み、遠藤の地元筆頭秘書として若かりし日の自民党総務会長の二階俊博氏らを育ててきた。数奇な縁からさまざまな職を経験した。今年11月に100歳。今でもその人望は厚い。
◇
政治家秘書は主人本位の一体感で臨まなければできません。経験を通じて政治ほど大変なことはなく、政治ほど大切なことはないと痛感しました。秘書に就いたきっかけは沼津中(現県立沼津東高)の恩師で、私たち夫婦の媒酌人だった前田千寸先生が「沼中卒の秘書になれる人を探している」と声を掛けてくれたこと。1953年1月から遠藤先生の沼津市の事務所で、書生ら5人ほどの取りまとめ役として働くことになりました。秘書としての始まりでした。
携わった選挙は3回目から。先輩秘書に教わりながら富士川以東の支援者回りなどを続け、血の小便が出たこともあったほど。遠藤先生が建設相として入閣して大臣秘書官を務めるなど選挙や秘書の仕事から多くの人脈ができました。二階俊博先生もその一人。中央大卒業後に秘書に加わり、選挙区にも頻繁に訪れてくれました。
秘書同士が立場を超えてまとまる場として「初心会」を発足しました。保守合同前の民主党幹事長だった岸信介氏が筆頭副幹事長の遠藤先生に贈った「初心忘るべからず」の一幅に由来しています。遠藤先生の命日12月27日を中心に集まって、しのんできました。
りーダーの資質学ぶ
遠藤先生は寡黙で地元のために献身した人でした。高速道路をめぐり東名か中央かどちらを先に着工するかという問題では意見を言いませんでした。土地を取られる農家に配慮した行動です。やると決断した時、決断後の行動は迅速でした。リーダーとして機を見るタイミング、決断すれば一気に動く行動力などを肌で学びました。
好きな書葉に「即離即覚(そくりそっかく)」があります。選挙に負けてもとちわれずに次を考える。くよくよしても仕方がないという意味です。遠藤先生の長兄が裾野市長選で敗れた時の言葉で、選挙の戦訓が万事に当てはまると自戒しています。遠藤先生は首都高速建設も力を注ぎ、首都高速道路公団が設立されると、私は秘書から公団調査役になり、遠藤先生の支援者でつくる遠藤会の原精一氏が沼津市長に当選した年からは、先生に言われて市企画部長として勤務しました。御用邸の払い下げ、東海大誘致などの課題を抱えていました。どれもこれまでに得た人脈が生き、実現や解決につながったと思います。
絶え間ない縁
書店の小僧から始まった人生を振り返ると、何回職業を変えたことか。行きたいという自分の意思で行ったところは一つもありません。次から次へと絶え間ない縁を与えてもらい、縁に従って生きた、いわば「随縁」です。縁は不思議です。どこでもここで一生働く気持ちで懸命に取り組んだ結果が次の縁につながってきたのではと思ったりもしますが、分かりません。
戦後70年です。真実を伝えることが生き残った人間の役目ですが難しい。近衛歩兵第2連隊に入隊し、翌年二・二六事件に巻き込まれました。戒厳令下鎮圧部隊の日々は忘れられない。その後は中国で第27師団支那駐屯歩兵第2連隊に転属し、師団司令部参謀部の作戦教育所属として打通作戦(大陸縦断作戦)にも参加しました。敗戦は広東から転進する途中で聞き、復員したのは31歳でした。
平和追求の努力を
仲間とともに戦後の郷土のために未来の道筋を考える場として「沼津自由大学講座」を企画しました。芹沢光治良や林芙美子、美濃部亮吉など各界を代表する人を講師に迎え、文化運動として結実しました。
「戦争はないほうが良い」。
誰もがそう思うでしょう。戦争をなくすためには、平素から皆で話し合い、英知を尽くして順序を踏んで平和を追求する努力をしなければならない。立派な政治家を輩出し、世界各国と話し、国内的には大同団結しないといけないでしょう。非常の時には非常の人が出てこないと非常を突破できません。
富士山に登るにもいくつもの道があります。一つの道でつっかえたら別の道を進む。道は一つではありません。お互いに助け合って良い方向を目指してほしい。同じ時代を生きているのだから。
『 遠藤三郎(1904-1971年)裾野市(旧富岡村)出身。旧制沼津中、第一高等学校、東京帝国大法律学科卒。農林省に進み食糧庁企画課長、和歌山県経済部長、農林省畜産局長などを歴任。1949年の総選挙で旧静岡2区より立候補して初当選し、衆院議員を連続9期務めた。大蔵政務次官や建設相のほか、自民党では副幹事長や政調副会長などの重職に就き、国土開発や農林水産業振興などに力を注いだ。狩野川台風の復旧には建設相として陣頭に立って対応した。』
(東部総局・杉山武博・宮崎隆男)
【静新平成27年5月1日「生きる」】
2015年12月23日
前田千寸先生
芹沢光治良ゆかりの地を訪ねてその9
「祖父・前田千寸と上野・東京美術学校」 天野博人

祖父前田千寸(まえだ・ゆきちか)は、明治十三年に高知県香美郡に生まれ、東京上野の東京美術学校を卒業した後、旧制中学の教員になりました。
最後の赴任先となったのが沼津中学で、その教え子だった井上靖さんや芹沢光治良さんに影響を与え、『夏草冬濤』や『人間の運命』などの作品に、千寸をモデルにした人物が登場しています。当時は下香貫に住んでいました。
その千寸が亡くなる前年の七十九歳の時、幼少期から東京美術学校在学時までの生活の回想を収録したテープがありましたので、その一部を紹介させていただきます。
大変な苦学を強いられた学生生活でしたが、教員となってからの沼中・東高時代を通じて、たくさんの生徒さんから慕われ、特に光治良さんからは特別な思いで接した要因が進祭できると思います。
ー東京美術学校本科一年生の終わり頃(明治三十五年)、我が家も村(高知県香美郡在所村)も経済状況が大変悪くなったので、学費を一切送れないから、学校を辞めて帰ってこいとのこと。帰ってみると、村で二人がタバコの密売をやり、それが専売局の手入れで発覚。村の連帯責任となり、その訴訟費用等で村全体が疲弊した。
学校を辞めるわけにもいかず、書生でもやればなんとかなるだろうと考え、従兄に紹介してもらった人から旅費、授業料、生活費三カ月分として五十円を借りて、新学期に学校へ行くも、すぐに高熱を出し、東大病院に無料で三週間の入院をさせてもらったが、これが学生時代を通じ最も優雅な時期であった。
書生先を探すべく、先生から紹介された所を訪ねるも、八時から十五時まで学校生活を送らねばならぬ者を置いてくれるところはなく、世の厳しさを思い知らされる。この時から苦学生生活が始まる。
下宿先も、その家の娘さんの勉強をみることと、さらに友達三人を呼んでくれば、との条件で入居。育英資金も月五円をもらい、授業料二十円、四回の分割払い。石版印刷、下絵描き等々いろいろなアルバイトにチャレンジするも駄目。当時はアルバイトが、それほどなかった。
そこで下宿先を二人で善光寺坂のお寺に移す。半値になった。自炊であったが、おかずはほとんどなく、味噌だけの時もあった。
しかし、木も買えず、お墓の塔婆とか、大工が黒板塀を壊して積んであるのを取ってきて薪にした。授業料を払うと、その月は全く金がなく、母が送ってくれた着物や、袷も一重にして、ほとんどは質入れ。不思議と私には言い値で貸してくれた。
六月二十日から九月十日は夏休みだが、家に帰る金がなく、友達の家に厄介になった。文展(日展)を知人の娘さんが見たいというので連れて行って、お寺へ帰ったら、そのような不謹慎者は置けないと言って下宿を追い出される。
友達と一緒に引っ越すも、ますます没落。三食付き五円、ただし、おかずなし。お米四合の約束も実際には三合。二年間、塩のみで食べる。
授業料を払うと、どうにもならなかった。腹が年中減っていた。絵の道具も買えず意気消沈。授業をサボり、木陰で青空を眺めていると、涙がとめどなく流れ、止まらなかった。
ある時、授業でモデル写生があったが、道具がないのでポカンと眺めていた。教授に呼ばれ、どうしたのか、青年時代にはよくあることだがと問われ、事情を話す。絵行燈(えあんどん)を描ぎたまえ、と一枚五十銭であった。十枚描いた。絵の偽装もやった。落款なしである。一枚一円二十銭。中国の武漠の絵が三円。牧野富太郎氏の模写が一冊五円、六冊描いた。それが学生時代のアルバイトの全て。柔道もやめた。
二食にして下宿代四円にしてもらうも、ますます腹が減った。絵の材料は借り買いにしてもらった。卒業まで。その点、今では考えられない。
塩だけでは、と味噌を無心に、お寺に行き、それを舐めた。煮物が、どうしても欲しくなると、友人の丸野君と闇夜に大根を五、六本失敬に行った。醤油を借りてきて煮たが、実に旨かった。三、四日は旨い思いをした。
石けんも買えず、二週間に一度くらい友達と一緒に風呂に行き、石けんを借りて洗うと垢がボロボロ出た。この頃、仙人生活を真剣に考え、霞を食っても生きていけると精神のあり方を変えたが、苦痛というものを感じなくなった。
五年間、制服は夏冬一着ずつで通したが、当時はバンカラで特別なことではなかった。
(前田千寸孫、沼津芹沢文学愛好会会員、根古屋)
【沼朝平成27年4月12日(日)号】
「祖父・前田千寸と上野・東京美術学校」 天野博人

祖父前田千寸(まえだ・ゆきちか)は、明治十三年に高知県香美郡に生まれ、東京上野の東京美術学校を卒業した後、旧制中学の教員になりました。
最後の赴任先となったのが沼津中学で、その教え子だった井上靖さんや芹沢光治良さんに影響を与え、『夏草冬濤』や『人間の運命』などの作品に、千寸をモデルにした人物が登場しています。当時は下香貫に住んでいました。
その千寸が亡くなる前年の七十九歳の時、幼少期から東京美術学校在学時までの生活の回想を収録したテープがありましたので、その一部を紹介させていただきます。
大変な苦学を強いられた学生生活でしたが、教員となってからの沼中・東高時代を通じて、たくさんの生徒さんから慕われ、特に光治良さんからは特別な思いで接した要因が進祭できると思います。
ー東京美術学校本科一年生の終わり頃(明治三十五年)、我が家も村(高知県香美郡在所村)も経済状況が大変悪くなったので、学費を一切送れないから、学校を辞めて帰ってこいとのこと。帰ってみると、村で二人がタバコの密売をやり、それが専売局の手入れで発覚。村の連帯責任となり、その訴訟費用等で村全体が疲弊した。
学校を辞めるわけにもいかず、書生でもやればなんとかなるだろうと考え、従兄に紹介してもらった人から旅費、授業料、生活費三カ月分として五十円を借りて、新学期に学校へ行くも、すぐに高熱を出し、東大病院に無料で三週間の入院をさせてもらったが、これが学生時代を通じ最も優雅な時期であった。
書生先を探すべく、先生から紹介された所を訪ねるも、八時から十五時まで学校生活を送らねばならぬ者を置いてくれるところはなく、世の厳しさを思い知らされる。この時から苦学生生活が始まる。
下宿先も、その家の娘さんの勉強をみることと、さらに友達三人を呼んでくれば、との条件で入居。育英資金も月五円をもらい、授業料二十円、四回の分割払い。石版印刷、下絵描き等々いろいろなアルバイトにチャレンジするも駄目。当時はアルバイトが、それほどなかった。
そこで下宿先を二人で善光寺坂のお寺に移す。半値になった。自炊であったが、おかずはほとんどなく、味噌だけの時もあった。
しかし、木も買えず、お墓の塔婆とか、大工が黒板塀を壊して積んであるのを取ってきて薪にした。授業料を払うと、その月は全く金がなく、母が送ってくれた着物や、袷も一重にして、ほとんどは質入れ。不思議と私には言い値で貸してくれた。
六月二十日から九月十日は夏休みだが、家に帰る金がなく、友達の家に厄介になった。文展(日展)を知人の娘さんが見たいというので連れて行って、お寺へ帰ったら、そのような不謹慎者は置けないと言って下宿を追い出される。
友達と一緒に引っ越すも、ますます没落。三食付き五円、ただし、おかずなし。お米四合の約束も実際には三合。二年間、塩のみで食べる。
授業料を払うと、どうにもならなかった。腹が年中減っていた。絵の道具も買えず意気消沈。授業をサボり、木陰で青空を眺めていると、涙がとめどなく流れ、止まらなかった。
ある時、授業でモデル写生があったが、道具がないのでポカンと眺めていた。教授に呼ばれ、どうしたのか、青年時代にはよくあることだがと問われ、事情を話す。絵行燈(えあんどん)を描ぎたまえ、と一枚五十銭であった。十枚描いた。絵の偽装もやった。落款なしである。一枚一円二十銭。中国の武漠の絵が三円。牧野富太郎氏の模写が一冊五円、六冊描いた。それが学生時代のアルバイトの全て。柔道もやめた。
二食にして下宿代四円にしてもらうも、ますます腹が減った。絵の材料は借り買いにしてもらった。卒業まで。その点、今では考えられない。
塩だけでは、と味噌を無心に、お寺に行き、それを舐めた。煮物が、どうしても欲しくなると、友人の丸野君と闇夜に大根を五、六本失敬に行った。醤油を借りてきて煮たが、実に旨かった。三、四日は旨い思いをした。
石けんも買えず、二週間に一度くらい友達と一緒に風呂に行き、石けんを借りて洗うと垢がボロボロ出た。この頃、仙人生活を真剣に考え、霞を食っても生きていけると精神のあり方を変えたが、苦痛というものを感じなくなった。
五年間、制服は夏冬一着ずつで通したが、当時はバンカラで特別なことではなかった。
(前田千寸孫、沼津芹沢文学愛好会会員、根古屋)
【沼朝平成27年4月12日(日)号】
2015年12月13日
中野翠さん
「いちまき」の中野翠さん
「操られている」感覚

「いちまき(一巻)」とは「一族」「血族」という意味の言葉。親戚から初めて聞いた時、「血がザワッとするような」生々しさを感じた。
エッセイストの中野翠さんが、幕末の動乱を生きた先祖をたどった新著を刊行した。「教科書に載るような話はないからすべてが消えていくと考えると、ちょっとでもくい止めたいと思いました」
きっかけは父の遺品を整理する中で見つけた曽祖母みわの回想録だ。
みわは1859(安政6)年に関宿藩(千葉県)の家老の養子木村正右衛門の娘として、江戸・桜田門付近にあった藩主の屋敷で生まれた。「桜田門外の変」の半年前だ。
藩に戻った正右衛門はやがて佐幕を主張して出奔、彰義隊と共に新政府軍と戦う。そんな激動の少女時代を、みわはあっけらかんと回想する。
ゆかりの地をめぐるうち、実家のかもいに飾られた写真でしか知らなかった老婦人が「すぐそこにいる人」のように感じられた。
「子供のころ、写真を見て、ひとくせありそうだと思った通りの女性。勝手に親近感を持っています」と笑う。
断片的な資料をつなぎ合わせ、「いちまき」をたどると、師範学校の教師となったみわの兄や、旧制一高に進みながら早世した弟も文章を残していたことを知った。
そして自身が好きな伊藤整の「日本文壇史」や山口昌男の「『敗者』の精神史」との意外なかかわりが浮かび上がるに至って、「操られている」という感覚を強くした。「自分の嗅覚や感受性だけで生きてきたつもりが、好き嫌いは私だけのものじゃなかったのかもしれないと思うと不思議な気持ちになりました」
生涯が判明した人、分からないままの人。たどれるかどうかは運や偶然も作用する。著者の探索を通じ、読者も歴史を感じ、自分の「いちまき」に思いをはせるだろう。
家族のことを話したことがなかった父が、みわの回想録を取っておいてくれたことがうれしかつた。「この本を書くことで、死者たちと語り合い、鎮魂できたのかもしれないと感じています」
(「いちまき」は新潮社・1512円)
【静新平成27年12月13日(日)この人この本】
「操られている」感覚

「いちまき(一巻)」とは「一族」「血族」という意味の言葉。親戚から初めて聞いた時、「血がザワッとするような」生々しさを感じた。
エッセイストの中野翠さんが、幕末の動乱を生きた先祖をたどった新著を刊行した。「教科書に載るような話はないからすべてが消えていくと考えると、ちょっとでもくい止めたいと思いました」
きっかけは父の遺品を整理する中で見つけた曽祖母みわの回想録だ。
みわは1859(安政6)年に関宿藩(千葉県)の家老の養子木村正右衛門の娘として、江戸・桜田門付近にあった藩主の屋敷で生まれた。「桜田門外の変」の半年前だ。
藩に戻った正右衛門はやがて佐幕を主張して出奔、彰義隊と共に新政府軍と戦う。そんな激動の少女時代を、みわはあっけらかんと回想する。
ゆかりの地をめぐるうち、実家のかもいに飾られた写真でしか知らなかった老婦人が「すぐそこにいる人」のように感じられた。
「子供のころ、写真を見て、ひとくせありそうだと思った通りの女性。勝手に親近感を持っています」と笑う。
断片的な資料をつなぎ合わせ、「いちまき」をたどると、師範学校の教師となったみわの兄や、旧制一高に進みながら早世した弟も文章を残していたことを知った。
そして自身が好きな伊藤整の「日本文壇史」や山口昌男の「『敗者』の精神史」との意外なかかわりが浮かび上がるに至って、「操られている」という感覚を強くした。「自分の嗅覚や感受性だけで生きてきたつもりが、好き嫌いは私だけのものじゃなかったのかもしれないと思うと不思議な気持ちになりました」
生涯が判明した人、分からないままの人。たどれるかどうかは運や偶然も作用する。著者の探索を通じ、読者も歴史を感じ、自分の「いちまき」に思いをはせるだろう。
家族のことを話したことがなかった父が、みわの回想録を取っておいてくれたことがうれしかつた。「この本を書くことで、死者たちと語り合い、鎮魂できたのかもしれないと感じています」
(「いちまき」は新潮社・1512円)
【静新平成27年12月13日(日)この人この本】
2015年12月11日
坂昭如さん死去
坂昭如さん死去

神奈川県鎌倉市生まれ。早稲田大文学部仏文科中退。63年、作詞した「おもちゃのチャチャチャ」が、レコード大賞童謡賞を受賞。68年に、敗戦と占領から日米親善という時代を生きる男の米国に対する屈折した心理を描く「アメリカひじき」と、終戦直後に栄養失調で亡くなった義妹をモデルに兄の記憶をつづりアニメ化もされた「火垂るの墓」で直木賞を受賞した。
「焼け跡闇市派」を名乗り、歌手としてもデビュー、映画への出演やキックボクシングに挑戦するなど多彩な活動で話題を呼んだ。72年、雑誌「面白半分」の編集長だった時、永井荷風作とされる「四畳半襖の下張」を同誌に掲載、73年2月、わいせつ文書販売の罪で起訴され、80年に有罪が確定する。
74年に参院選に立候補して落選。83年に参院比例代表区で当選するが、同年に辞職し、田中角栄元首相の衆院旧新潟3区から立候補。金権政治の打破を訴えたが、次点で落選した。
97年に「同心円」で吉川英治文学賞、02年に「文壇」とそれまでの業績により、泉鏡花文学賞を受賞。戦争を忘れてはいけないという思いから、「戦争童話集」の作成に取り組んだ。
「ソ、ソ、ソクラテスかプラトンか」で人気を呼んだテレビCMや討論番組でもおなじみだった。03年に脳梗塞(こうそく)で倒れ、リハビリを続けていた。(朝日デジタル)

神奈川県鎌倉市生まれ。早稲田大文学部仏文科中退。63年、作詞した「おもちゃのチャチャチャ」が、レコード大賞童謡賞を受賞。68年に、敗戦と占領から日米親善という時代を生きる男の米国に対する屈折した心理を描く「アメリカひじき」と、終戦直後に栄養失調で亡くなった義妹をモデルに兄の記憶をつづりアニメ化もされた「火垂るの墓」で直木賞を受賞した。
「焼け跡闇市派」を名乗り、歌手としてもデビュー、映画への出演やキックボクシングに挑戦するなど多彩な活動で話題を呼んだ。72年、雑誌「面白半分」の編集長だった時、永井荷風作とされる「四畳半襖の下張」を同誌に掲載、73年2月、わいせつ文書販売の罪で起訴され、80年に有罪が確定する。
74年に参院選に立候補して落選。83年に参院比例代表区で当選するが、同年に辞職し、田中角栄元首相の衆院旧新潟3区から立候補。金権政治の打破を訴えたが、次点で落選した。
97年に「同心円」で吉川英治文学賞、02年に「文壇」とそれまでの業績により、泉鏡花文学賞を受賞。戦争を忘れてはいけないという思いから、「戦争童話集」の作成に取り組んだ。
「ソ、ソ、ソクラテスかプラトンか」で人気を呼んだテレビCMや討論番組でもおなじみだった。03年に脳梗塞(こうそく)で倒れ、リハビリを続けていた。(朝日デジタル)
2015年12月03日
青島正和さん(あおしままさかず)(沼津市)
沼津御用邸記念公園西付属邸で個展を開催している
青島正和さん(あおしままさかず)(沼津市)

個展会場は110年前に天皇の御用邸として設置された木造平屋建ての建物。墨や和紙、アクリル絵の具、金銀の箔(はく)で端正な図形を描く近作など30点を展示した。66歳。
ー由緒正しい和風建築での展覧会。
「『モダンな和』をイメージして描いた平面作品を畳敷きの和室に置いた。格調高い空間が絵を引き立たせ、自宅で見るのとは全く異なり、驚いた。思いがけない出合いだと感じた」
ー「和」を主題に創作を始めたきっかけは。
「約10年前、琳派(りんぱ)の画家酒井抱一の『夏秋草図屏風』を見て感動したこと。尾形光琳や俵屋宗達ら琳派の色彩や構図に漂う、モダンな感覚にあらためて気付かされた。自分も和紙や墨などを取り入れて、和の現代性を追求しようと考えた」
ー描き続ける原動力は。
「1973年から所属する地元の美術集団『グループ風土』の存在。メンバー間で作品を批評し合う例会や、年2回の展覧会が創作の後押しになっている」
ー絵を描くとはどんな行為か。
「とても苦しいこと。絶望を何度も味わいながら、ようやく完成にたどり着く。その瞬間ほっとし、満足感を得る。この繰り返しを50年以上続けている」
◇
静岡大での恩師は洋画家の故長岡宏さん。2008年度まで田方地区の小中学校で美術を教えた。
【静新平成27年12月3日(木)この人】
青島正和さん(あおしままさかず)(沼津市)

個展会場は110年前に天皇の御用邸として設置された木造平屋建ての建物。墨や和紙、アクリル絵の具、金銀の箔(はく)で端正な図形を描く近作など30点を展示した。66歳。
ー由緒正しい和風建築での展覧会。
「『モダンな和』をイメージして描いた平面作品を畳敷きの和室に置いた。格調高い空間が絵を引き立たせ、自宅で見るのとは全く異なり、驚いた。思いがけない出合いだと感じた」
ー「和」を主題に創作を始めたきっかけは。
「約10年前、琳派(りんぱ)の画家酒井抱一の『夏秋草図屏風』を見て感動したこと。尾形光琳や俵屋宗達ら琳派の色彩や構図に漂う、モダンな感覚にあらためて気付かされた。自分も和紙や墨などを取り入れて、和の現代性を追求しようと考えた」
ー描き続ける原動力は。
「1973年から所属する地元の美術集団『グループ風土』の存在。メンバー間で作品を批評し合う例会や、年2回の展覧会が創作の後押しになっている」
ー絵を描くとはどんな行為か。
「とても苦しいこと。絶望を何度も味わいながら、ようやく完成にたどり着く。その瞬間ほっとし、満足感を得る。この繰り返しを50年以上続けている」
◇
静岡大での恩師は洋画家の故長岡宏さん。2008年度まで田方地区の小中学校で美術を教えた。
【静新平成27年12月3日(木)この人】
2015年12月03日
園田勝さん(そのだまさる)沼津青年会議所の理事長
高校生や企業と連携し商品開発に取り組んだ 沼津青年会議所の理事長
園田勝さん(そのだまさる)(清水町)

2010年に入会し、日本青年会議所(JC)東海地区静岡ブロック協議会役員、沼津JC副理事長を歴任した。おでんで有名な居酒屋「飛騨」(沼津市大手町)を経営する。40歳。
ー10月下旬に「『自慢のコレ』高校生×企業コラボ甲子園」を主催した。
「沼津の新しい土産を作り出そうと、高校生と企業がスクラムを組んで開発した新商品の発表の場。5月から開発を進めてきた6チームが新製品を披露し、大好評だった。実際に売れている商品も出ている。高校生は勉強になり、企業にもいい刺激になったはず」
ー企画した目的は。
「高校生に郷土愛を育んでもらうのが狙い。人口流出が全国でも顕著な沼津。大学進学で沼津を離れた高校生が就職の際に戻るためにも今回の企画を通して地元を好きになってほしかった。高校生が一番楽しめていたようでうれしかった」
ー活動の成果は。
「高校生や地元の企業のために取り組んだことが結果的に沼津のためになったという実感がある。沼津JCの会員も裏方として一生懸命に支えてくれた。関わったみんなが成長できた」
ー沼津JCへの思いは。
「会員が同じ土俵で意見を言い合い、自らの成長につながる。今後も仲間を増やしながら、失敗を恐れず前に進む組織でありたい」
◇
店では「自分が作った料理でお客さんを笑顔にする」を心掛ける。
【静新平成27年12月2日(水)この人】
園田勝さん(そのだまさる)(清水町)

2010年に入会し、日本青年会議所(JC)東海地区静岡ブロック協議会役員、沼津JC副理事長を歴任した。おでんで有名な居酒屋「飛騨」(沼津市大手町)を経営する。40歳。
ー10月下旬に「『自慢のコレ』高校生×企業コラボ甲子園」を主催した。
「沼津の新しい土産を作り出そうと、高校生と企業がスクラムを組んで開発した新商品の発表の場。5月から開発を進めてきた6チームが新製品を披露し、大好評だった。実際に売れている商品も出ている。高校生は勉強になり、企業にもいい刺激になったはず」
ー企画した目的は。
「高校生に郷土愛を育んでもらうのが狙い。人口流出が全国でも顕著な沼津。大学進学で沼津を離れた高校生が就職の際に戻るためにも今回の企画を通して地元を好きになってほしかった。高校生が一番楽しめていたようでうれしかった」
ー活動の成果は。
「高校生や地元の企業のために取り組んだことが結果的に沼津のためになったという実感がある。沼津JCの会員も裏方として一生懸命に支えてくれた。関わったみんなが成長できた」
ー沼津JCへの思いは。
「会員が同じ土俵で意見を言い合い、自らの成長につながる。今後も仲間を増やしながら、失敗を恐れず前に進む組織でありたい」
◇
店では「自分が作った料理でお客さんを笑顔にする」を心掛ける。
【静新平成27年12月2日(水)この人】




