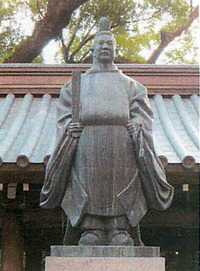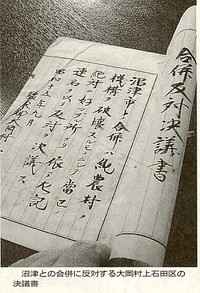2008年03月10日
本居宣長
本居宣長
「源氏物語千年⑧」島内景二.
「もののあはれ」見抜いた宣長
本居宣長(一七三〇年ー一八〇一年)の著作を読むと、底なしの学力に恐ろしくなる。人間は努力すれば、ここまで思索を高められるのだ。源氏物語を最も深く読んだ日本人は、宣長だろう。
北村季吟が「湖月抄」で集大成したのは、それ以前の読み方だった。その伝統的な解釈史を、宣長はたった一人で見事にひっくり返した。
 宣長の代表作は「古事記伝」だが、源氏物語の魅力を縦横に論じた柵玉の小櫛(おぐし」もまた、奇跡の書である。季吟が過去の解釈のすべてを踏まえて、「この文章はこう解釈するのが穏当だ」と整理したので、普通の読者ならばすんなりと納得する。だが宣長は、平然と膨大な個所の異議申し立てを行う。ほとんどの場合、宣長の新解釈の方が深い。
宣長の代表作は「古事記伝」だが、源氏物語の魅力を縦横に論じた柵玉の小櫛(おぐし」もまた、奇跡の書である。季吟が過去の解釈のすべてを踏まえて、「この文章はこう解釈するのが穏当だ」と整理したので、普通の読者ならばすんなりと納得する。だが宣長は、平然と膨大な個所の異議申し立てを行う。ほとんどの場合、宣長の新解釈の方が深い。
しかも宣長は、この物語の大前提である「光源氏の年齢」を正確に計算し、季吟までの学者が犯していた年齢の間違いを訂正した。現在市販されているテキスト類は、自明のように「この巻は光源氏の十七歳から翌年までを描く」などと説明しているが、この数字は宣長が計算し直した数字である。
天才的な分析力と論理力を武器に、深く正しく本文を読み抜いた宣長は、源氏物語の生命力の正体を見抜き、「もののあはれ」と名づけた。
論理の人である宣長は、何と情緒の人でもあったのだ。人間は、理屈で人を好きになったり、死者を哀惜するのではない。腹の底からこみあげてくる、自分でも説明できない根源的な感情があって、それに突き動かされて、泣いたり笑ったりするのだ。それが「もののあはれ」である。
光源氏は、最も大きな「もののあはれ」を抱いて苦しんだ人間だった。そう語る宣長は、紫式部が源氏物語を書かずにはいられなかった「暗い宿命」を見つめていた。なぜ紫式部はこの物語を書いたのか。自分でもわからない、せっぱ詰まった情動が、彼女を動かしたのだ。
宣長が没して、二百年以上になる。彼以後の研究者は、まだ「もののあはれ」にかわる源氏物語の生命力を発見できていない。それほど、宣長がこの物語から発見した心の闇は深かった。(電気通信大教授)
(静新平成20年3月10日「命をつなげた人々」)
「源氏物語千年⑧」島内景二.
「もののあはれ」見抜いた宣長
本居宣長(一七三〇年ー一八〇一年)の著作を読むと、底なしの学力に恐ろしくなる。人間は努力すれば、ここまで思索を高められるのだ。源氏物語を最も深く読んだ日本人は、宣長だろう。
北村季吟が「湖月抄」で集大成したのは、それ以前の読み方だった。その伝統的な解釈史を、宣長はたった一人で見事にひっくり返した。
 宣長の代表作は「古事記伝」だが、源氏物語の魅力を縦横に論じた柵玉の小櫛(おぐし」もまた、奇跡の書である。季吟が過去の解釈のすべてを踏まえて、「この文章はこう解釈するのが穏当だ」と整理したので、普通の読者ならばすんなりと納得する。だが宣長は、平然と膨大な個所の異議申し立てを行う。ほとんどの場合、宣長の新解釈の方が深い。
宣長の代表作は「古事記伝」だが、源氏物語の魅力を縦横に論じた柵玉の小櫛(おぐし」もまた、奇跡の書である。季吟が過去の解釈のすべてを踏まえて、「この文章はこう解釈するのが穏当だ」と整理したので、普通の読者ならばすんなりと納得する。だが宣長は、平然と膨大な個所の異議申し立てを行う。ほとんどの場合、宣長の新解釈の方が深い。しかも宣長は、この物語の大前提である「光源氏の年齢」を正確に計算し、季吟までの学者が犯していた年齢の間違いを訂正した。現在市販されているテキスト類は、自明のように「この巻は光源氏の十七歳から翌年までを描く」などと説明しているが、この数字は宣長が計算し直した数字である。
天才的な分析力と論理力を武器に、深く正しく本文を読み抜いた宣長は、源氏物語の生命力の正体を見抜き、「もののあはれ」と名づけた。
論理の人である宣長は、何と情緒の人でもあったのだ。人間は、理屈で人を好きになったり、死者を哀惜するのではない。腹の底からこみあげてくる、自分でも説明できない根源的な感情があって、それに突き動かされて、泣いたり笑ったりするのだ。それが「もののあはれ」である。
光源氏は、最も大きな「もののあはれ」を抱いて苦しんだ人間だった。そう語る宣長は、紫式部が源氏物語を書かずにはいられなかった「暗い宿命」を見つめていた。なぜ紫式部はこの物語を書いたのか。自分でもわからない、せっぱ詰まった情動が、彼女を動かしたのだ。
宣長が没して、二百年以上になる。彼以後の研究者は、まだ「もののあはれ」にかわる源氏物語の生命力を発見できていない。それほど、宣長がこの物語から発見した心の闇は深かった。(電気通信大教授)
(静新平成20年3月10日「命をつなげた人々」)
Posted by パイプ親父 at 12:05│Comments(0)
│歴史上の人物