2020年11月21日
第63回沼津朝日賞決まる 松下宗柏師
第63回沼津朝日賞決まる
命のビザ杉原夫妻の顕彰碑
建立に尽力した松下宗柏師
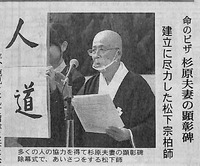
1948年、鹿児島市生まれ。73年、東京外国語大学英米語学科を卒業し、日本貿易振興会(ジェトロ)に勤務したが、75年に三島市の龍澤寺(臨済宗妙心寺派)で修行に入る。
7年間の修行の後、長興寺(大塚本田)の住職に就任。当時35歳、「こちらへは骨を埋める気持ちで参りました」と語っている。
いわゆる「余所者」として沼津に来た松下師が、最初に行ったのが近所の子ども達を対象とした寺子屋英語教室の開設。子どもを通じて地域の人達との信頼関係を築くと広く門戸を開き、坐禅会などを行ってきた。「無」を求め共に座り続ける坐禅会は、現在も続く。
さらに、地域のにぎわいづくりのために、と始めたのが「奉納泣き相撲大会」。今では沼津における初夏の風物詩として定着し、初期の頃に出場した赤ちゃんが親となって、生まれた子を出場させるようにまでなった。
一方、「白隠を読む会」を原地区センターで地域の有志と共に開き、白隠の心と歴史に触れる機会を約10年間にわたって設けてきた。同会における年1回の公開講座では、医師の帯津良一氏や白隠研究家の芳沢勝弘氏など一流の講師を招き市民に学びの場を提供した。
そうした寺や地域を地盤とした活動を続ける中で、今年は「六千人の命のビザ」の人道的な行為で知られる杉原千畝(すぎはら・ちうね)、それを支えた幸子(ゆきこ)夫人の2人を顕彰しようと記念碑の建立を思い立った。
そもそものきっかけは2018年、坐禅を紹介するためにリトアニアを訪ねたこと。杉原の行いにどれほど尊い意味があったのか、現地で目の当たりにする。さらに、それを支え続けた幸子夫人が沼津出身であることを知り、沼津の人にも広く知ってもらいたいと願った。
そして今年、杉原の生誕120年、命のビザ発給から80年の節目を捉え、夫妻を顕彰する記念碑を建立しようと、多くの人の賛同と協力を得て、わずか半年で完成を見ることとなった。
今月開かれた除幕式には在日リトアニア大使やイスラエル大使館広報官も出席。また、前駐リトアニア全権大使による講演会も開き、同国や杉原夫妻への理解を深める機会も設けた。顕彰碑は建立が終わりではなく、その精神を次の世代に伝えていくことが目的だからだ。
「若い世代の人に、沼津への誇りを持ってほしい」と松下師は願い、いずれの機会にも高校生の参加を呼び掛けてきた。若い人に託す希望は大きく、見守るまなざしは温かい。
沼津朝日賞の受賞について、「やっと沼津市民として認められた。足が地に着いたような思い」だと言い、今後の抱負については「道は自ずから開けていく」と語っている。
【沼朝令和2年11月21日(土)号】

命のビザ杉原夫妻の顕彰碑
建立に尽力した松下宗柏師
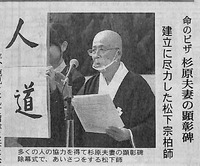
1948年、鹿児島市生まれ。73年、東京外国語大学英米語学科を卒業し、日本貿易振興会(ジェトロ)に勤務したが、75年に三島市の龍澤寺(臨済宗妙心寺派)で修行に入る。
7年間の修行の後、長興寺(大塚本田)の住職に就任。当時35歳、「こちらへは骨を埋める気持ちで参りました」と語っている。
いわゆる「余所者」として沼津に来た松下師が、最初に行ったのが近所の子ども達を対象とした寺子屋英語教室の開設。子どもを通じて地域の人達との信頼関係を築くと広く門戸を開き、坐禅会などを行ってきた。「無」を求め共に座り続ける坐禅会は、現在も続く。
さらに、地域のにぎわいづくりのために、と始めたのが「奉納泣き相撲大会」。今では沼津における初夏の風物詩として定着し、初期の頃に出場した赤ちゃんが親となって、生まれた子を出場させるようにまでなった。
一方、「白隠を読む会」を原地区センターで地域の有志と共に開き、白隠の心と歴史に触れる機会を約10年間にわたって設けてきた。同会における年1回の公開講座では、医師の帯津良一氏や白隠研究家の芳沢勝弘氏など一流の講師を招き市民に学びの場を提供した。
そうした寺や地域を地盤とした活動を続ける中で、今年は「六千人の命のビザ」の人道的な行為で知られる杉原千畝(すぎはら・ちうね)、それを支えた幸子(ゆきこ)夫人の2人を顕彰しようと記念碑の建立を思い立った。
そもそものきっかけは2018年、坐禅を紹介するためにリトアニアを訪ねたこと。杉原の行いにどれほど尊い意味があったのか、現地で目の当たりにする。さらに、それを支え続けた幸子夫人が沼津出身であることを知り、沼津の人にも広く知ってもらいたいと願った。
そして今年、杉原の生誕120年、命のビザ発給から80年の節目を捉え、夫妻を顕彰する記念碑を建立しようと、多くの人の賛同と協力を得て、わずか半年で完成を見ることとなった。
今月開かれた除幕式には在日リトアニア大使やイスラエル大使館広報官も出席。また、前駐リトアニア全権大使による講演会も開き、同国や杉原夫妻への理解を深める機会も設けた。顕彰碑は建立が終わりではなく、その精神を次の世代に伝えていくことが目的だからだ。
「若い世代の人に、沼津への誇りを持ってほしい」と松下師は願い、いずれの機会にも高校生の参加を呼び掛けてきた。若い人に託す希望は大きく、見守るまなざしは温かい。
沼津朝日賞の受賞について、「やっと沼津市民として認められた。足が地に着いたような思い」だと言い、今後の抱負については「道は自ずから開けていく」と語っている。
【沼朝令和2年11月21日(土)号】




